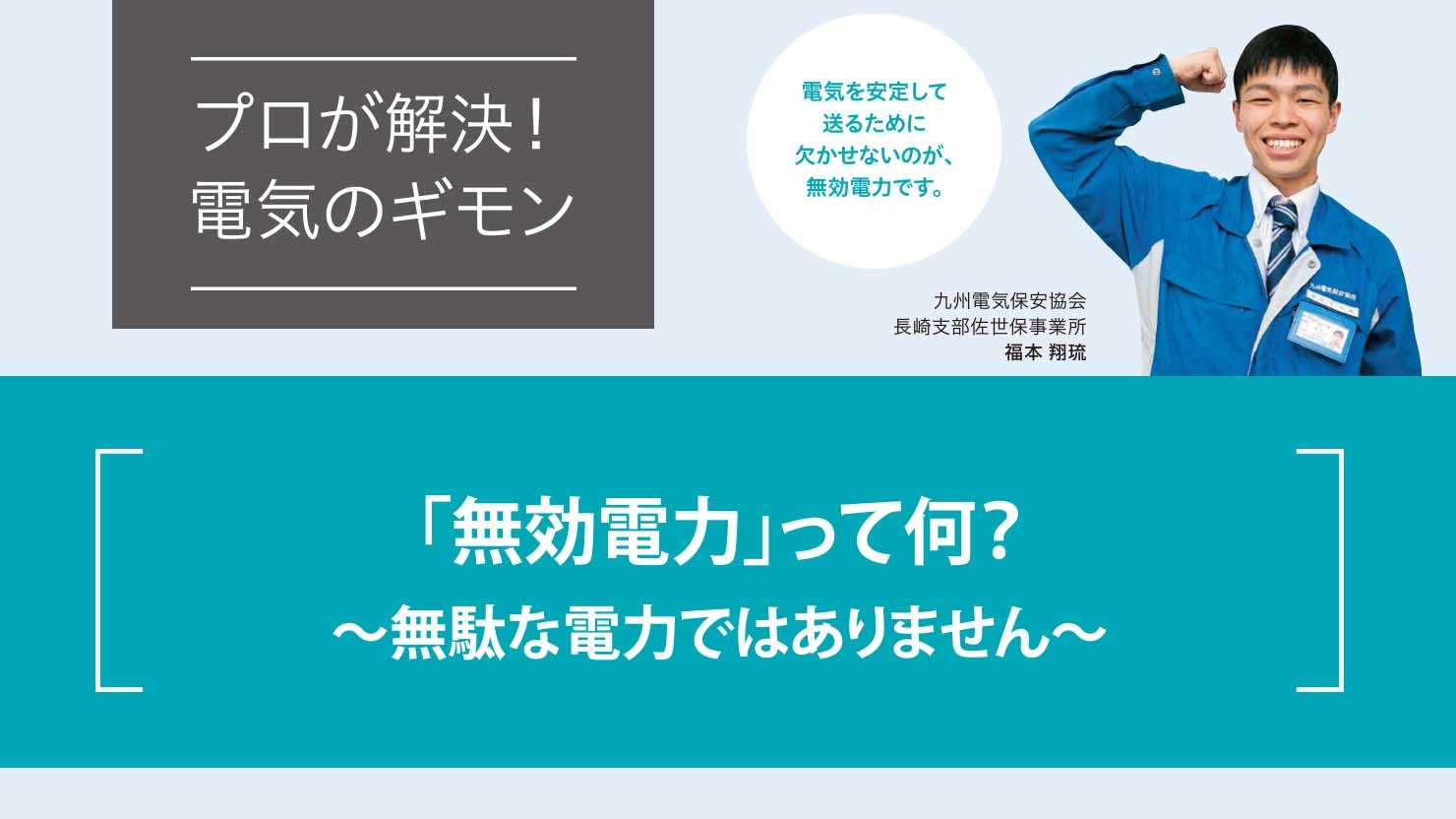
プロが解決!電気のギモン
「無効電力」って何?
~無駄な電力ではありません~
電力会社から供給されて家庭や事業所などに送られてくる電気は交流ですが、その電力は皮相電力(単位VA、kVA)と有効電力(単位:W、kW)、無効電力(単位:var、kvar)の3種があります。
そのなかの無効電力とはどんなもので、どんな働きをしているのか。電気保安のプロである当協会の電気主任技術者がご説明します。
電圧を上げ下げする無効電力
家庭に通常配電されているのは交流100Vの電力。この電力の中の有効電力が照明やテレビ、エアコンなどさまざまな家電製品(負荷)に供給されて消費されます。だから有効電力=消費電力です。一方、無効電力は、電圧と電流が常に波として一定周期で大きさが変化する交流で、電圧と電流の変化のタイミング(位相)がずれてくると発生し、負荷で消費されずに電源と負荷との間を往復するだけです。
ただし、モーターなどに使われるコイルに電気が流れると無効電力は消費されます。そして無効電力が消費されるとコイルを流れる電気の電圧が下がります。反対に、電気を蓄えたり放出したりするコンデンサに電気が流れると無効電力が発生してコンデンサを流れる電気に供給され、このときに電圧が上がります。電気を使うときにコイルが多いと電圧が下がり、コンデンサが多いと電圧が上がるのです。

送配電系統を安定させる無効電力
無効電力の働きをうまく利用しているのが送配電系統です。送電で重要なことは、電気の供給量と電気の消費量が常に一致していること。そこで供給側(電力会社)は消費側の電力需要が高い日中にはそれに合わせた大きな電力を、需要が低くなる夜間には小さな電力を送っています。ところが送電線は、送る電力が大きいと受電側の電圧が送電側より下がり、送る電力が小さいと電圧が上がってしまいます。
電圧が不安定な電気は使いづらいので、供給側では受電側の電圧を一定に保つため、変電所に大きなコイルやコンデンサを設置。大きな電力を送るときは、コンデンサをつないで無効電力を供給し、電圧が下がりすぎないようにします。逆に小さな電力を送るときは、コイルをつないで無効電力を消費させ、電圧上昇を防ぐのです。無効電力は、送配電系統を安定させる調整役だといえるでしょう。


